中学生の頃、英語がどうしても頭に入らなかった。
発音も文法も“知っているようで知らない”ものばかりで、努力しても空回りしていく感覚がありました。それでも今、大人になって振り返ると、あのときの“できなさ”にはちゃんと理由があったように思います。
知っているのと違った、最初のつまずき
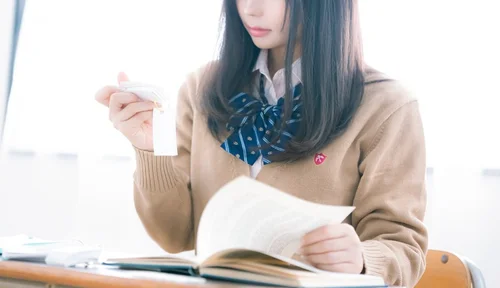
ローマ字との違いが混乱の始まり
英語との出会いは、“未知の言語”というよりも、「知っているはずのものが違う」という違和感から始まりました。
ローマ字との混乱、発音のギャップ、そして“英語らしく読む”ことへのためらい。
当時はそれをどう処理していいかわからず、『アルファベットは知っているのに読めない』『聞いたのに書けない』ことが増えていきました。
発音とスペルの不一致に戸惑う
耳で聞いた音と、教科書で見るつづりが一致しない。
頭では理解していても感覚がついてこない。
「なぜ読まない音があるの?」という疑問が、英語を『正しく読もうとするほど混乱するもの』に変わっていきました。
“英語らしく話す”ことへの恥ずかしさ
当時は発音を真似するのが少し照れくさくて、英語を上手に読むことが「目立つこと」のように感じていました。
今思えば、あの頃の“恥ずかしさ”も小さな壁の一つでした。
文法がわからなかった、というより“なじめなかった”
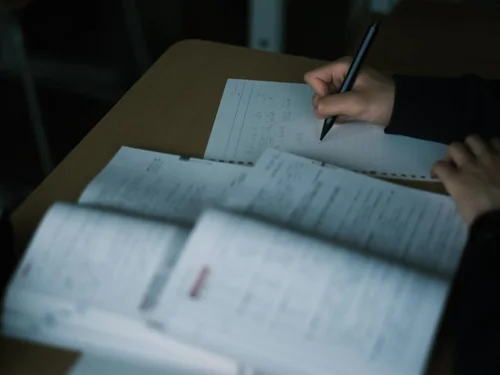
be動詞=動詞?というモヤモヤ
be動詞や主語・述語などのルールを教わっても、“なぜそうなるのか”が腑に落ちませんでした。
「ここにbe動詞を入れます」と言われても、“なぜisやareが動詞になるの?”というモヤモヤが残る…。
『be』が付いているのでおかしな感じがしますが、日本語で言えば助動詞ですよね。
日本人同士の会話で『あ〜これは助動詞だな。』って意識しながら話してますか?
そんな人いないですよね!?
教科として勉強するために何かに当てはめなければいけない。
今思えば、そんな中学校教育自体にモヤモヤしていたのかもしれません。(笑)
丸暗記に納得できない性格
それなら丸暗記で!といって覚えられる人もいるかもしれません。
しかし、丸暗記すれば済むとわかっていても、納得できないまま覚えるのはどうしても苦手でした。
“正解を出すこと”=テストの点。そんな学生時代に私の『なんで?」『どうして』はあまりにも不適合でした。
英語ができなかったのは、“必要”を感じなかったから

保育士を目指していた私に、英語は不要だった
英語を頑張る理由が、当時の私には見えませんでした。
それは中学生の頃にはすでに「将来は保育士になりたい。」と決めていたからです。
それも目指していたのは公務員保育士。私立の英語をセールスにした保育園や幼稚園を目指すなら話は変わってきますが、私のビジョンにそれは1ミリもありませんでした。
数学も化学も同じ“必要性の壁”
実は、数学も化学も同じでした。
どちらも「保育士になるのに、どこで使うんだろう?」と感じていたんです。
数学で言えば、方程式を覚えても将来役に立つイメージが持てませんでした。
でも今思えば、壁面製作のレイアウトを考えたり、
手芸で作りたい物のサイズを計算したりするとき、
あのときの数学の知識が活きる場面ってたくさんある。
“学んでおけばこんな良いことがある”というビジョンが見えていなかっただけなんです。
化学も同じ。中学までは理科が楽しかったのに、
高校に入ってからはいきなり元素記号の羅列。
「は?ですよね。」と思ったのを今でも覚えています。
でももし、化学を“化粧品づくり”や“身近な科学”として学んでいたら、
もっと興味を持てたのかもしれません。
“動機づけ”の欠如
私には、動機づけが必要だったんです。
「これを学ぶと自分の世界がどう広がるのか」。
その“先のイメージ”を持てなかったから、必要ないと感じた瞬間に心のシャッターを下ろしてしまったのだと思います。
結局、私にとって勉強のモチベーションは、“自分に関係があるかどうか”がすべて。
だから興味の偏りも自然なことだったのかもしれません。
だって私は保育に興味があったから。
音楽や手芸、運動、国語に気持ちが向くのも当然でした。
今になって思うのは、どんな教科も“興味の持ち方”次第で世界が変わるということ。
それを、子どものうちに自然と感じられる環境があれば——。
子どものうちに“興味”を持てる環境をつくることが、いちばんの近道

英語を“世界とつながるツール”として感じられたら
もし中学生の頃の私が、英語を“勉強”ではなく“世界とつながるもの”として感じていたら、
きっともう少し興味を持てたと思います。
今の子どもたちは、YouTubeで海外の動画を見たり、アニメの主題歌を英語で口ずさんだりと、自然に触れる機会がたくさんあります。
でもそれも、“英語って楽しそう”と思えるきっかけがあってこそ。
今振り返ると、英語が“勉強”ではなく“世界とつながるもの”として感じられていたら、もう少し違ったかもしれません。
親が楽しそうに英語で会話している姿を見る。
それだけでも、子どもは自然と興味を持つと思うんです。
日本語だってそう。
スプーンの持ち方も歩き方も、親の背中を見て覚えていきます。
親がやらないのに子どもだけに「やりなさい。」と言っても、それは自主性ではなく“やらされている”になってしまう。
“やりなさい”より、“一緒にやってみよう”の方が、学びの楽しさが自然と伝わる気がします。
苦手の理由を見つめ直してわかったこと
英語が苦手だった本当の理由は“最初の入り口”
英語が苦手だったのは単に努力不足だったのではなく、『最初の入り口』が間違っていたのではないかと思っています。
ローマ字を習う前に『美しい=Beautiful』というように、言葉と意味をそのまま『そういうものだ。』と認識できていれば、きっと「ビアウティフル。」とは覚えなかった。
つまり環境とタイミングが何より大切なんです。
学びの始まり方1つで“得意”の道か“苦手”の道か、歩み方が変わっていく。
でもそんな学びの大切なポイントを私はもう30年以上過ぎてしまいました。
だからこそ、今の自分にできることは—?!
大切なポイントが過ぎているからと言って、学べないわけではありません。
どう学んでいくか、『学びの環境を整える』ことが必要不可欠なのです。
自分に合ったやり方は何なのか…。
学習という既存の型にハマらずに、これからも英語と向き合い続けていきます。
大人になってからの勉強の仕方
英語の学び直しを始めてから、私が最初に選んだのはオンライン英会話でした。
次の記事では、そこで感じたことや自分なりの『英語との付き合い方』について書いてみようと思います。
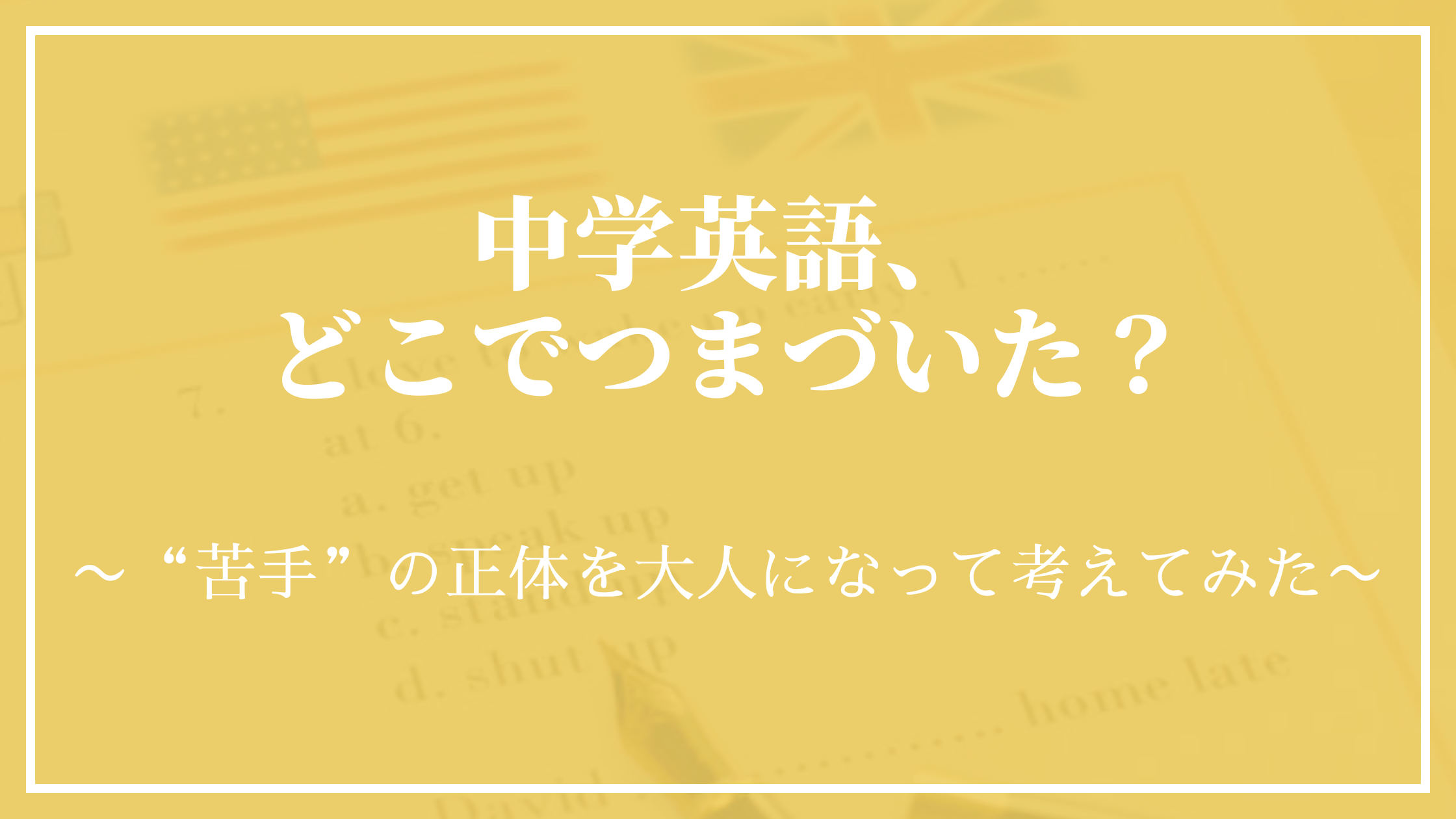
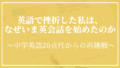
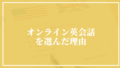
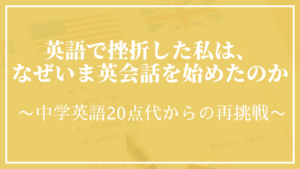
コメント